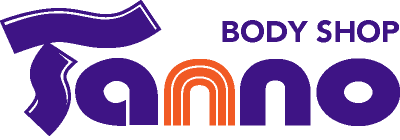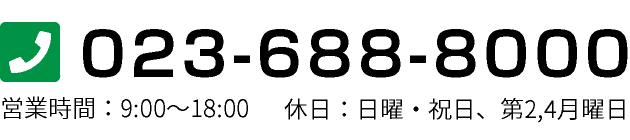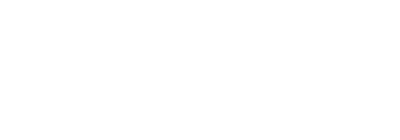春の七草粥
年も明けてから7日目
一年の最初の節句
「人日の節句」

七草の若芽を食べて食物がもつ
生命力を取り入れ
無病息災でいられるように願いを込めて
「七草がゆ」が食べられるそうです
春の七草と言えば

『 せり、なずな、、
ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、、
すずな、すずしろ、、
はるのななくさ 』
と、五・七・五・七・七
短歌のリズムて覚えるといいですよ


芹(せり)
せり科の多年草
古事記や日本書紀にも記録がある
古くから食用にされていました

薺(なずな)
アブラナ科の年越草
実の形が三味線に似ていることから
日本では、ぺんぺん草とも呼ばれています

御形(ごぎょう)
キク科の年越草
喉の痛みの緩和やデトックス効果があり
ハーブティーとして人気が高まっています

繁縷(はこべら)
ナデシコ科の年越草
中国では古くから薬草として
歯磨き粉などに使用されていたそう

仏の座(ほとけのざ)
キク科の年越草
食用のコオニタビラコを指していて
黄色い小さな花を咲かせます

菘(すずな)
アブラナ科の蕪(かぶ)
弥生時代頃の中国から伝わったそうです

蘿蔔(すずしろ)
アブラナ科の大根
風邪予防や美肌効果が期待できるとか

最近のブログ記事
2025/12/04
2025/12/01
2025/11/27
2025/11/01
2025/11/01
お知らせ
2025/11/15
2023/04/04
アーカイブ
![]()